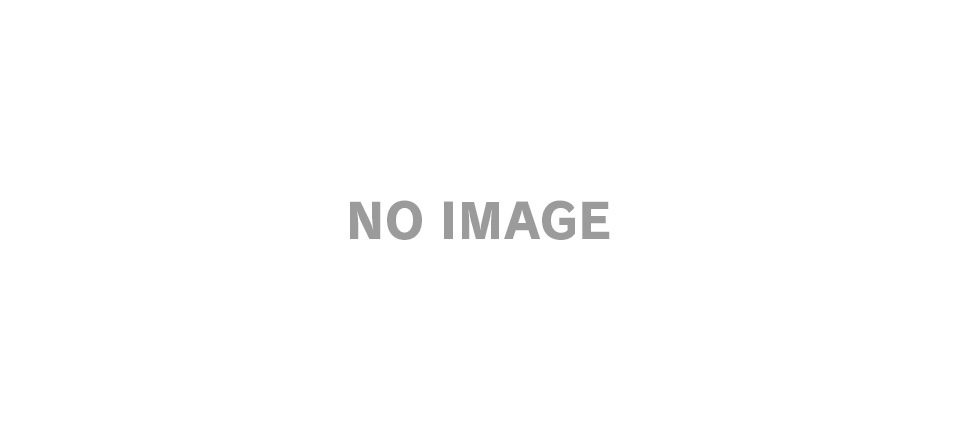- 浜さ恋Top
- トラベル・ライター, 地元記者
- 双葉町ツアー 〜 町の人々の“記憶”という文化と価値を伝えていく〜
双葉町ツアー 〜 町の人々の“記憶”という文化と価値を伝えていく〜

双葉町は大熊町とともに東京電力福島第一原発が立地する町である。町民は全国各地に散り、海外へ避難している世帯もある。町は町民不在のまま時を重ね、ようやく解除への一歩を踏み出したのは、震災から9年後の2020年のこと。この年の3月4日、双葉町の避難指示解除準備区域や双葉駅周辺の一部解除と、特定復興再生拠点区域内の立ち入り規制緩和が出された。とはいえ避難指示解除対象区域は全町の4%で、駅前と東日本大震災・原子力災害伝承館や町の産業交流センターなどが新設された沿岸部がその主な対象地域だ。その駅を囲むように設定された周辺区域は特定復興再生拠点区域に再編され、2022年6月以降の避難指示解除を目指し、準備宿泊が始まってはいるが、町内のほとんどは帰還困難区域のまま、除染土や汚染廃棄物を保管管理する中間貯蔵施設に指定されている地区も抱え、町の再生に向けての課題は山積みなのが現実だ。
JR常磐線双葉駅の駅舎前に集う。この駅舎は2020年に以前の駅舎を残す形でリニューアルされコミュニティスペースとなっている。旧駅舎に取り付けられている町民からも愛されていたからくり時計は2時46分を指している。駅から6号国道までの1本の道は解除され通過できるが、その両側は立ち入りができるものの帰還困難区域だ。除染や解体が進み、空き地が目立つ商店街に、月日を経て朽ちた建物がポツポツと見える。不在がもたらす独特の乾いた空気を打ち消すように、建設中の町の仮設庁舎の工事の音が、冬空にこだましていた。
「皆さんようこそおいでくださいました」
双葉町を歩きながら巡るツアーの案内人として駅前で待っていてくれたのは、双葉町民の山根辰洋さんだ。双葉郡地域観光研究協会の代表理事を務め、現在双葉町の議員としても活躍する双葉町の若手の1人。辰洋さんは家族と共に双葉町が現在役場機能を置くいわき市に住んでいる。2013年に支援者として町に関わり始め、結婚を機に双葉町民となった辰洋さんは、双葉町のことを町民目線から知ってもらおうと、2020年からツアーの案内人をしている。
「私が双葉町に来た当初の2013年は、双葉町は30年間は帰れないと言われていた場所でした。それが大きな転換があり、2020年3月に一部地域が解除になり、電車も開通して、こうやって皆さんをお迎えできるようになった。これは奇跡のようなことだと思っており、今日は皆さんとこうして双葉町で出会えたことを嬉しく思っています」
そんな語りから、辰洋さんのツアーははじまった。


歩き出すとすぐ目に入ってくるのは、壁いっぱいに描かれた大きな女性の顔とその隣に描かれた“HERE WE GO”の文字。これらを描いたのは、OVER ALLsという東京のアートカンパニー。この場所でバーを営んでいた店主が避難先の東京で店を出し、そこに、このアートカンパニーのメンバーが来店したのが縁で町中の様々な壁面へのペイントが実現したのだそうだ。その横に描かれている明るい笑顔が印象的な女性は、学生たちに人気だったファーストフード店「ペンギン」の名物ママだ。当初アイスとジュースを出すお店として開店したこのお店、冷たいイメージのある動物の名前にしよう!となり、トド、シロクマ、なども候補にあがる中、ペンギンに決まったという。震災前にお店は閉店していたものの、現在は、産業交流センターにお店を再創業している。双葉町の “ファーストペンギン”になったと、辰洋さんは案内をしながら語る。双葉町を守る存在として「ペンギン」の名物ママは今日もここで町を見つめているのかもしれない。


そのようにして辰洋さんから語られるかつての町の姿に、私たちはゆっくりと歩きながら引き込まれていった。そこで暮らした人々の話や消防団隊員の方たちの話、自分たちが立つこの場所で行われていた「ダルマ市」、夏の双葉町の風物詩でもあった盆踊りのこと、はたまた時には戦国時代に遡り、広大な空き地にかつて存在していた建物の話が飛び出すなど、目にしている風景とは別の光景が生きた言葉で語られ、私たちは町を歩きながら、実際にあるものを見るだけではなく、ここで生きた人々の記憶を旅しているのだと、徐々に気がつきはじめる。
商店街エリアを抜け、かつて“明るい未来のエネルギー”という看板がかかっていた場所を抜け、復興復旧に向けて行き交う大型トラックを見ながら、6号国道を越えると、かつて住宅地となっていたエリアに入る。現在ほとんどの家は取り壊しで更地となり、残る家はまばらだ。野原となった風景の奥には、震災時に避難所としても活用されていた双葉町役場の茶色い建物も見えた。

残された家の一つに「山根」という表札が掛かっている。その家は、辰洋さんの妻、光保子さんが住んでいた実家だという。雑草が茂る庭を歩いた先に、屋根が朽ちかけた家のガラス戸から見える部屋は、淡いピンク色のジャケットや柔らかそうな毛布が敷かれたベッド、小さなキャビネットなどが置かれ、その床はびっしりと隙間なく緑色の苔が覆っていた。苔の間から植物が芽を吹き窓のあかりを受けて成長し、部屋を見渡せば置かれたすべてのものに植物の枯葉がホコリとともに降り積もっている。原子力災害がもたらしたこと。財産とは。この町の人たちが失ったものが何であったか。暮らしというものは、個人の人生の積み重ねそのものだった。

「思い出アルバムがなくなった感じがするんだよねっていう話をしてくれた方がいました。自分の人生の中の、何かが抜け落ちちゃってるみたいな感じがすると。故郷喪失イコール人生の一部を喪失することなんですね。その人がそれまで歩んできた人生。そこから強制的に切り離されて他の場所に行かざるを得なかったっていうのが、どれほどのことかっていうのが、自分でも恥ずかしいですが、ここに来るまでは実感としては分からなかったんです」
山根辰洋さんは、結婚前は小林辰洋さんだった。東京の八王子市に生まれ育ち、少年時代は野球に明け暮れる日々を送った。恩師との縁で映像に興味を持ち、映像クリエイターとして働きはじめたのは2010年。1年経たないうちに、東日本大震災・東京電力福島第一原発の事故が起きた。首都圏からさらに南へと避難した方が良いのではないかという情報までもが飛び交う中、辰洋さんはネットなどを使って、何が起きているのかを自分なりに調べはじめた。そこで初めて、自分が使っている電気が福島で作られていたことを知り、知らなかった自分にも愕然とした。「自分にも関わりがあることで大変な思いをしている人たちがいるのに、自分は何もしなくていいのか」辰洋さんの弟やその仲間たちがいち早く募金サイトの立ち上げに奔走する動きに加わり、辰洋さんは自分のスキルで東北の役に立てればと、映像制作などでのプロボノの活動を始めたのが東北との縁が繋がるきっかけとなった。
震災の年、12月末に会社を辞める。余裕ができた時間の中で、自分ができることは何かと探しているその時、東北復興支援団体の人員募集情報が入ってきた。これだ!辰洋さんの勘が囁き、即座に応募。東北の復興支援の伴走者としてコンサルティングをしていくような会社に入ったのだった。
岩手や宮城での仕事が続いた後の2012年の冬。仕事の一環で、当時は埼玉の加須市にある旧騎西高校に役場機能を置いていた双葉町に相談を受け、足を運ぶことになった。古い校舎の教室には畳が敷き詰められ、生活感が染み込んでいた。この環境下で集団生活を1年半以上も送り続けている双葉町の人々の姿を見て、言葉を失った。同じ日本においてこれほど長い期間、避難所での生活をせざるを得ない状況があっていいのか。モヤモヤとしながら、町をサポートする支援者の採用や配置などのスキームを整える仕事にあたった。その計画を作る中で、町役場に身を置きながら情報発信支援する人材が必要となり、辰洋さんは気がつけば「私がやります」と手を挙げていた。
2013年の6月には双葉町は役場機能を、より双葉町に近いいわき市に移転することを決定。8月に赴任した辰洋さんはいわき市に移住。数名でのチームを組みながらの復興支援の仕事がスタートした。このチームにいたのが、のちに結婚することになる双葉町民の山根光保子さんだ。支援のニーズを把握するため、まず住民一人ひとりの声を聞こうと、芋づる式に人を紹介してもらいながら避難先を訪ね歩いた。町民に何が必要かを聞いていくと、そこに見えてきたのは、かつてのコミュニティーの喪失だった。隣近所知り合いばかりの双葉町では、常日頃から人と人の会話があり、そこでの日常の小さな出来事もお互いに渡し合うような関係が築かれていたこと。町の行事や祭りが活発な地域では、しょっちゅう町の人たちが集まっていたこと。コミュニティーの再生には、コミュニティーを維持するためのご近所情報のようなものがまずは必要だということが分かった。
その中で初めに取り組んだのは、「つなげよう つながろう ふたばのわ」というコミュニティ紙の発行だ。町民が実施するイベントや活動などを記事にして毎月届け、webでも見られるように掲載した。そしてそれと並行して、全国各地に散らばっている町民同士の繋がりを維持するために双葉町が導入を決定した、タブレット端末配布の取り組みを支援した。
辰洋さんは、双葉町に関わるまで、人の話をこれほどまでに聞いたことは無かった。多くの経験をしてきた方達の話は示唆に富み、地域の繋がりを大切にしてきた双葉町の人たちの考え方は、東京で生まれ育った辰洋さんにとって新鮮でもあり、コミュニティーというものが本来どういうものなのかを学ぶ機会でもあった。丁寧に語りを聞く時間を作りながら、まだ見ぬ双葉町への愛着だけは深まっていった。
2014年の3月、辰洋さんは同僚の山根光保子さんの一時帰宅に同行させてもらい、初めて、双葉町内を訪れた。ずっと見てみたかったリアルの双葉町。町民の人々の語りの中に想像していた双葉町が、目の前にあった。かつて山の上にはお城があったこと、町民が大事に維持してきた神社のこと、ダルマ市という正月の行事では巨大ダルマの綱引きが行われていたこと、地区それぞれの神楽や盆踊りはそれぞれ特徴があり地区ごとで文化を守っていたこと、高校生たちに愛されていたお店のこと、ラーメン屋さんのこと、体育館で行われた結婚式のこと、住んでいた家のこと。今まで数多くの町民の方に会いながら受け止めてきた双葉町の記憶が情景として視界に流れ込み、目の前の風景と重なっていく。失われてしまったもの。一方で、双葉町の地域性や歴史や暮らしの営みは、町の人々の記憶の中にも息づいていた。その可視化できないものの中にこそ、無形ではあるがかけがえがない価値があり、町のアイデンティティーが含まれていたのだと思った。
支援員としての最後の年、辰洋さんは、その双葉の伝統文化を未来に残しておこうと、映像に残すことにも取り組んだ。3年で任期は終わる。しかし辰洋さんにとっては既に、双葉町の人たちは自分自身を形作ってくれた生みの親のようなものだった。大切な人たちに幸せでいてほしい。恩返しをしたい。そんな気持ちもある中で、山根光保子さんとの結婚の話も持ち上がった。支援者ではなく住民として町に関わることは、自分にとっても嬉しいことだと辰洋さんは思った。その選択はどこかでホッとすることでもあった。これだけ大きな課題に対して3年では出来ることは限られていると思っていたからだ。「これから50年かけて取り組めばいいんだ」そう思った。小林辰洋さんは、山根辰洋さんになった。

ツアーの最後、修復された相馬妙見初發神社をお参りした。この神社は相馬藩によって建立され、この地域のコミュニティの人々が集まり、守る場として、ずっと続いてきた神社なのだそうだ。震災で社殿の柱が傾きそのまま放置されていたのを、氏子の人々が発起し資金を集めて柱を建て直し、再建に至った。2020年、御神体がこの場所に戻され、その晩、闇に沈む双葉町の街中に灯った神社のあかりは“これが本当の復興の光だ”と感じたのだという。
神社に手を合わせ、そこから歩くとすぐに双葉駅が見えてきた。町を実際に歩いてみることで、生活者としての感覚でその場所が見えてくる。ここに暮らしていた人たちが大切にしていたことに触れること。それが失われたことで何を感じているのかを想像すること。目には見えない“記憶”という財産。連綿とこの場所で人々が紡いできた暮らしの証。語りとともに巡ることで、ここを出発した時と今では、違う感覚がすでに宿っている。
「まずは気軽に来てもらいたいですね。それが絶対、再生の原動力になる。「観光」と言っていますが、本来観光というのは平和だからこそ成り立つものなんです。このツアーも今は観光とは言えない。でもだからこそ、胸を張って観光地と言える状況を目指して進もうとすることに意味がある。観光目線になることで客観的に見えてくる物事があるからです。現実は正直言ってまだまだ厳しいです。それでも逃げずにその現実を見ること。そこでチャレンジできることはたくさんあると思うんです。コミュニティーの核は“人”だと僕は思うんです。神社のように、1人の核となる存在があれば、呼び水となってそこからコミュニティーが形成されていく。その1人、1人を重ねていけば、ちょっとずつですが可能性が見えてくる。その再生の種を受け入れる拠点として自分はここで町民としての発信をしていこうと思っています」。
辰洋さんは「50年でこの町の再生が終わるとは思っていない」と言う。「礎だけ作ってバトンを渡す準備くらいまではしたいと思っています」そう飄々と語る山根辰洋さんという呼び水から再生されていくコミュニティーはどんな未来を描いていくのだろう。難題を抱えながらも、ようやく一歩を踏み出そうとしているこの町で、一つの勇気が小さな波紋を生み出そうとしていた。

文・写真 藤城 光
<福島双葉タウンストーリーウォーキングツアー>
運営:一般社団法人双葉郡地域観光研究協会
住所:福島県双葉町大字新山字久保前48番地の1
料金:3,000円
所要時間:約1.5時間
問い合わせ先
一般社団法人双葉郡地域観光研究協会
電話番号 070-5074-9804(山根)
※多くの観光施設やイベント及びキャンペーンが新型コロナウィルス感染症の影響で一時閉鎖・中止・延期になっています。状況は日々変動しますので、訪問前に主催者の公式ページでご確認ください。
※掲載の情報は2022年1月時点のものです。