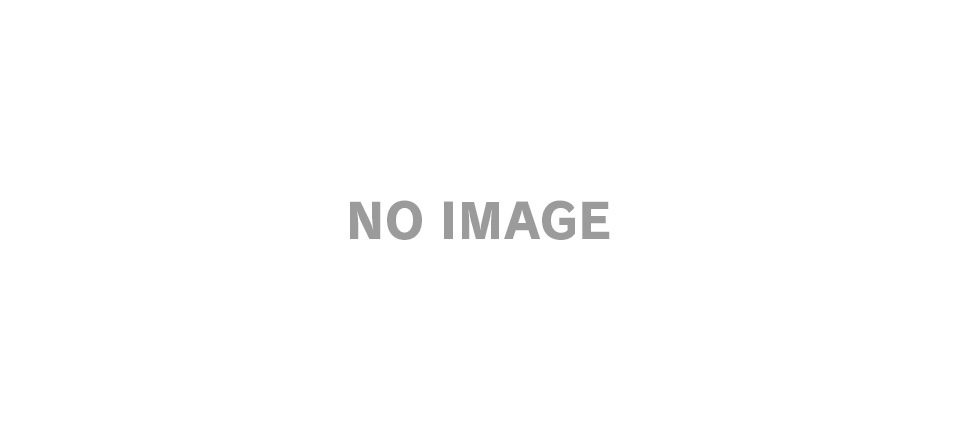- 浜さ恋Top
- トラベル・ライター, 地元記者
- 納得できる生き方を 〜喫茶ヤドリギ〜
納得できる生き方を 〜喫茶ヤドリギ〜

“生きる、とは?”という問いを中心に据え、集まっている若者たちがいる。彼らは、津波と原発事故の影響を受け、約4年半の全町避難を余儀なくされ、その後2015年9月5日避難解除となり再起に向けて歩み出した楢葉町で暮らしている。時間を作っては集まるその顔ぶれは現在、松本昌弘さん、森亮太さん、西﨑芽衣さん、森雄一朗さん、日野涼音さん、後藤采納さん(と、昌弘さんと芽衣さんの娘の灯ちゃん1歳)らが中心となっている。多くのものが失われたこの場所で自分という存在を探り、その身を土地に投げ打つように奮闘している面々だ。
今取り組もうとしているのは「カフェ」というスタイルで場を開いていくこと。そのカフェの名前は「喫茶ヤドリギ」。様々な人たちにサポートしてもらいながら、かつての姿からは様変わりしてしまった楢葉町竜田駅近くに、誰もが立ち寄れる小さな生命の樹のような拠点を作ろうとしている。
その一つの起点となっているのは、楢葉町の公務員として働いている松本昌弘さんの存在だ。昌弘さんは楢葉町で生まれ育ち、津波で家を失い、原発事故で町を離れることを余儀なくされた。町の公務員として波乱の時期の町を支え、大きな喪失からの立ち上がりに邁進しながら、自分が生まれ育った故郷と自分に向き合い続け、個人の活動として「生きるための芸術。」というプロジェクトを主催、体の奥底から揺れあがるような表現を様々な形で発信し続けている。「震災があって失ったものは大きかったが、震災があったからこそ得られたものもあった筈だ。震災があったからこそ納得できる生き方をしたい」という彼の考え方・生き方に触発された者も数多いるだろう。その結果、集まってきたのがこのメンバーとも言えるかもしれない。
昌弘さん以外は、県外からきた若者たちである。そのうち3人は、立命館大学在学中に結成したボランティアチーム「そよ風届け隊」の活動をを組織通じて、京都から福島へと通い続けた学生たちだ。そして発端を作ったのが森亮太さんであり、共に立ち上げに関わったのが西﨑芽衣さん。そしてのちに加わった学生の中に、森雄一朗さんがいた。彼らは京都から深夜バスを使って福島に行き、いわき市の仮設住宅に住まう楢葉町の人々への足湯を提供しながらおこなう傾聴活動などのボランティアや、町の人との文通、町の人と人を繋ぐ「ならはかわら版」というフリーペーパーの発行など、楢葉町の人々と共に活動をかたち作ってきた。震災や原発事故からの日々を歩み続ける町や人々との関わりは、彼らの心に、福島に実際に住みながらそこで生きる人々と共に生きていきたいという気持ちを芽生えさせていった。「お前は悔いのないように生きているか?」と自己内省を突きつけるような昌弘さんの存在もまた、それぞれの決断の後押しをしていくこととなる。
そして森亮太さんは、大学卒業と同時に楢葉の宿泊温泉施設での業務を見つけ移住を決意。その仕事と並行して「ならはかわら版」作りの編集・デザインにあたった。するとそこからデザインを頼まれることが増え、翌年にはなんとデザイナーとして独立。それと同時に、2017年より始まった復興庁の「復興・創生インターン」という課題解決型インターン生のメンターも担うようになった。さらに楢葉町の起業型地域おこし協力隊にも着任。楢葉町の中に人が集える拠点を作ることを描きながら、その事業化へも向かいはじめた。ぼんやりと浮かんでいたのは、アートや音楽、文学など表現に関わる人たちが集える場。着地点は見出せずにいたものの、拠点となる物件探しをはじめたのだった。
亮太さんらと共に立ち上げから活動してきた西﨑芽衣さんは、京都と福島の往復をするうちに「もっとじっくりと時間をかけて町の人々と関わりながら地域のために働きたい」との思いを抱いた。ちょうど2015年の楢葉町の解除とその後を見据え立ち上がったまちづくりのための法人「一般社団法人ならはみらい」が立ち上がったことを知り、臨時職員を希望。大学を1年休学し楢葉町の多くの人が避難していたいわき市に移住し働きはじめたのだった。その後いったん大学に戻るも、卒業後の進路として家族の反対を押し切って選んだ道は楢葉町で働くことだった。ならはみらいの職員となり町の人々にも慕われる存在として活躍している芽衣さんは、楢葉で出会った松本昌弘さんと2019年に結婚。2020年末には娘が誕生した。決意のこもった彼女の瞳の奥にはまだ避難解除となる前の誰もいない楢葉の町の情景を見た時の衝撃が残り続けている。それがこの町に生活者として降り立ち生きる意志を支えているのかも知れない。
そんな先輩たちの背中を見ながら「そよ風届け隊」の活動に参加していたのが森雄一朗さんである。元々彼は人付き合いが得意な方ではなかったのだそうだ。そんな自分を変えたいという思いもあり始めたのがこのボランティアでもあった。そして、フリーペーパー「ならはかわら版」を作るにあたっての住民インタビューで楢葉の人々の話を深く聞き、楢葉の人々の人柄や抱擁力に触れるうちに、自分の考えがどんどん変化し、世界が広がっていくのを感じた。そして出会った昌弘さんの「震災があったからこそ納得できる生き方をしたい」という言葉に感銘を受けた。いつしか彼らのいる楢葉で働きたいとの思うようになった雄一朗さんは、まずは力をつけようと地元群馬の銀行に就職。しかし実際に仕事が始まると楢葉に行く時間も減り、精神的距離が出来てしまう環境に歯痒さがつのり、再び自分の人生を問い直し出した結論は、楢葉町への移住。その選択を反対する人も多かったが就職後1年を待たず退職し、芽衣さんが働く「一般社団法人ならはみらい」へと就職。楢葉町の住民となったのだった。
一方で、森亮太さんがメンターを務める「復興・創生インターン」に2019年に参加していたのが、当時大学1年生だった日野涼音さんと後藤采納さんである。
日野涼音さんは現在、山形県にある東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科4年。1年生の時にインターン先として選んだのが芽衣さんや雄一朗さんが働いている「一般社団法人ならはみらい」だった。岩手、宮城、福島にまたがるこのインターン事業の中で楢葉を選んだ理由には涼音さんの父親の存在があった。涼音さんの父親は東日本大震災を機に何年かの間、単身赴任の形で楢葉町に隣接する富岡町に住み、震災復興に関わる仕事にあたっていたのだ。父が何を思いながら福島の復興に従事していたのか。どこかで気になっていた福島の復興。そういった気持ちが重なり、彼女は福島へ向かった。そしてそこで出会った楢葉町の人々との交流の中で、ここで生きる人の、この楢葉の風景や生き方への想いの強さに触れ、もっと近くで関わりたいという気持ちが強くなっていった。そして大学4年の1年間、ならはみらいのインターンをしながら、楢葉町で卒業研究を行うことにした。
一方の後藤采納さんは大分出身で現在は新潟県・長岡造形大学建築環境デザイン学科の4年生だ。彼女が子どもの時に起きた東日本大震災。地震を感じることもなく、遠くで起きているその出来事の大きさに対して、子どもゆえに何も出来ない自分に無力感を持った。高校生の時に熊本・大分での大地震や九州豪雨での洪水が起き、ボランティアを経験。その後大学に入り「復興・創生インターン」という復興庁のプロジェクトで被災地に実際に行けることを知り、その中でも「新しいコミュニティーをカタチにせよ」という課題に惹きつけられ、采納さんは楢葉町へのインターンの参加を申し込んだのだった。そしてやはりそこで湧いてきたのは、短期間ではなく日常的な視点で住んで町を見つめたいという想いだ。一見では見えない心の内側にある被災のあり方が気になっていった。その後4年生になり、彼女もまた卒論研究の対象として楢葉町を選び、偶然にも同じ選択をした涼音さんとルームシェアをしながら楢葉町で暮らすことを決めたのだった。
その2020年の冬のことだった。楢葉町の竜田駅新設のため、今まで使われてきた旧駅舎が12月に取り壊されることとなった。それ受けて、住民で地域のことを考えようと組織された “竜田駅西側を考える会”と、その会に関わっていた昌弘さんたちから「旧駅舎のお別れ会をしたい」という話がもちあがった。その話を聞いた涼音さんと采納さんと亮太さんもその提案に協力をすることになり「ありがとう、竜田駅」というイベントを実施することが決まった。竜田駅の思い出の写真を集めることとなり、駅舎の模型の展示と合わせ、お別れ会に来る人たちが思い出を語れるようにと楢葉町のジオラマも作成することに。時間が無い中で、3人は楢葉の地図や等高線図を準備し涼音さんと采納さんそれぞれが所属する大学の力も借りてジオラマ作成へと奔走した。1畳程の大きさにスチレンボードの重なりで、山や川、海などの地形が現れる。そこに小さな家々や学校、お寺やお店など、震災前にあった風景が立ち上がっていく。雄一朗さんも仕事からあがると顔を出し、芽衣さんは臨月を迎え大きなお腹を支えながら旧駅舎を覗いた。
12月2日〜11日の1週間、イベント期間中に駅舎へ訪れた人々が、かつての楢葉町を互いに懐かしみ、ジオラマとして現れたかつての町の姿を眺めながら思い出話を語りだす。そして色とりどりの紙がついた小さな旗に思い出を書き込んで該当の場所に差し、町が思い出に彩られてゆく。外からきた人たちがジオラマを町の人と囲んで、興味津々にその話を聞くこともあった。人々が頬を寄せ合い、懐かしい話に花を咲かせているその姿を、明治時代から楢葉を見守ってきた小さな旧駅舎が、暖かく包み込んでいた。
旧駅舎に集う人々の姿を見ながら、亮太さんの脳裏には、地域おこし協力隊の事業としてずっと悩んでいた拠点のイメージが湧いていた。自分がやりたい拠点というのはこういうことなのではないか?と彼は思った。ちょうど昌弘さんと、この地域で拠点作りをすることについて話していた時期でもあった。こんなふうに人々が集い、語り合える場を作ろう。亮太さんはさっそく、昌弘さん、芽衣さん、雄一朗さん、涼音さんと采納さんに相談を持ちかけた。どんな拠点とするのが良いのか、どう運営していくのが良いのか、彼らと一緒に構想を練り、作りたいと、思った。すぐに昌弘さんと芽衣さんは竜田駅前の空き物件の情報を亮太さんへと繋いだ。その空間づくりをサポートしてくれる人たちとの出会いもあり、新しい仲間も加わった。新しい夢のはじまりだった。

その頃、昌弘さんと芽衣さんの子ども“灯ちゃん”が産まれ、いつしかその話し合いは灯ちゃんがいる松本家の新居で行われるようになった。夜な夜な集まって語らう彼らの言葉は常に本音だ。新居のダイニングにはポストイットが天井まで貼られ、時に白熱しながら、結論が難しい話にあきらめずに向かい続けている。どんなコンセプトとしていくのか、誰がどう運営に関わるのか、空間はどう作り上げていくのか、町の人たちに日常的に使ってもらうにはどうするか。その話をする時間そのものが、彼らの生きる糧となっているようにも見えた。
それぞれが強い熱量を持ち、互いが互いを補完し合うような関係は、作ろうと思って作れるものではない。今後去る人もいれば加わる人もいるだろう。しかし変化しながらもきっと、その熱が向かう先には「生きる」ということを問い、損得など関係のないところで命の軸を燃やし続ける存在があるに違いない。そんな彼らが運営する「喫茶ヤドリギ」はきっと、今は失われた旧駅舎がかつてそうだったように、寄せられた人々をあたたかく包み、熱のある想いをそっと渡しあえるような、ここにしかない場所となってゆくだろう。

<喫茶ヤドリギ オープン時期・営業時間など>
2022年春オープン予定
営業時間未定
文・写真 藤城 光